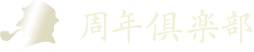膨大な情報の加工や分析といった途方もない作業の連続。それは歴史を編むプロセス。
●膨大な資料に目眩が
「社史の執筆なんて、爺さんライターがやる仕事」
フリーランスのライターになって4年が経過した1999年、まだ42歳だった私にとって、社史執筆の仕事は、そんなイメージでした。出版界が斜陽を迎え、執筆を担当していた雑誌がポツリポツリと廃刊になっていくご時世ではありましたが、それでも継続している定期物はあったし、時代の先端に関わる仕事に携わっていたいというのが本音。老境の仕事には、相当な抵抗がありました。
いくつか、部分的なお手伝いを経て、本格的にがっぷりよつで取り組んだ社史は、2002年に刊行されたコンクリート橋梁メーカーの50年史が初めてでした。元勤務先だった制作会社から私に声がかかったのは1999年ごろのこと。「爺さん仕事はイヤだなあ」と思いつつ、諸般の事情で渋々請け負った仕事でした。まさか、ここで社史執筆の面白さに目覚めるとは想像もできませんでした。
最初に面食らったのは、資料の膨大さです。雑誌の単発仕事なら、せいぜい一束か二束の資料で済みますが、社史の資料は段ボール箱単位で次々と送られてきます。歴代の社内報全号や関連団体の年報、技術資料、工事記録集……原本を預かるわけにはいかないので、たいていは片面コピー。紙の枚数は倍になります。
これをとりあえず本棚に詰め込んだところ、間もなく本棚は重さに耐えかねて、ものの見事に座屈・崩壊しました。頑丈そうな本棚を新調して並べ直し、ひとまずは安堵したわけですが、この膨大な資料に目を通さないといけないのかと思うと、くらくらと目眩さえ感じます。
●縦糸と横糸が紡がれる瞬間
通常、原稿を書くという作業には、大きく分けて2つの段階があると思います。まずは情報収集(Input)、そして執筆作業(Output)です。必要最低限の資料収集や取材というInputを経て、Outputに進む。雑誌やPR誌の数ページ程度の仕事なら、この2段階でおおむね事足ります。
しかし社史の場合はInputの情報量が膨大なので、とても小さな頭には入りそうにありません。重要そうなページに適当に付箋をつけて、そのつど参考資料にしながら書いていくのも方法でしょうが、これでは、いくつもの「点」が無秩序に散らばったような原稿になってしまう。「社史」である以上、その会社が歩んできた道程、すなわち「線」で歴史を捉えることが必須ですから、賢い方法ではなさそうです。
困り果てていた時に思いついた方法の一つが、とりあえず、自分用に社内報の索引を作ることでした。1号ごとに斜め読みし、そこに書かれた内容の意味も専門用語も解読できないまま、とりあえず索引のようなものを作り、そこに、「有用そうな詳細記事」とか「時代背景の説明あり」などと、備忘録のメモをつけていくわけです。
それはそれは、途方もない作業の連続で、たぶん1カ月か2カ月、ひたすら毎日、朝から晩までインデックス作成に精を出していたように思います。「こんな作業に意味はあるのか」と自問自答しつつ、さりとて、何から手を付けたらいいのか皆目見当もつきません。苦し紛れに始めた苦肉の策でしたが、これが後に大正解と判ります。取材でお聞きした話と社内報に出ていた記事が紐付けできるようになり、事業進展の前後関係がだんだん見えてきます。口頭でお聞きした話を社内報で補完して、だんだんと情報に血肉がつき始めてくる実感も湧いてきます。
Excelデータなどでいただいた年表情報の類も、自分用にあれこれ書き加えて徹底的にカスタマイズしました。取材で得られた情報、業界他社や関連団体の動きを加えて、どんどん、自分専用の資料に仕立てていきます。
そんな地味な作業を何か月も重ねていくうちに、ある日「あっ」と気づくわけです。茫洋として掴み所がなかった会社の歴史に、縦糸が見え始め、関連部署や社会との繋がりを示す横糸が見え始め、会社の歴史という織物が、ふわっと頭の中に浮かび始めていることを。社史ライターとしての快感に、初めて目覚めた瞬間でした。
●歴史を編むプロセス
社史ライターとして、もう一つ快感を覚えることがあります。それは、原稿を提出し始めた後の打合せや、完成後の慰労会で、担当者から時折いただく、こんな言葉。
「ウチの社員よりも、よっぽど、ウチの会社のことに詳しいんじゃないですか」
これ、最高の褒め言葉です。表面的には「いえいえ、とんでもないです」などと平静を装ってはいますが、内心では悦びマックス、犬がビュンビュン尻尾を振っているような心境です。社史という歴史の編み物をきちんと織り上げることができて、良かった。達成感をしみじみ味わえる瞬間です。
先に、原稿執筆作業には情報収集(Input)と執筆作業(Output)があると記しました。でも社史制作ではInputとOutputの間にある情報加工や分析(Process)にどれだけ真摯に取り組めるかが勝負で、ここが腕の見せ所だし、最終的に仕上がる社史の良否を決めるキモになると思っています。そしてProcessの大切さを理解してくれる辛抱強い編集者がサポートしてくれること。これも欠かせません。
歴史を編むプロセスを大切にして、喜ばれる社史を作りたい。これからも、社史執筆の面白さにのたうち回りたい。つくづく、そう思います。